子どもには拡大、障害者には削減。それが森市長の“選別行政”
「市民の声を聞く」と言ったその口で、
声を上げられない市民を切り捨てるとは――。
◆ “助けられていた制度”が削られるという衝撃
館山市で約半世紀にわたり続けられてきた、中軽度障害者への医療費助成制度。
それはただの金銭的補助ではない。日々の通院、精神的な安心、そして「この町は自分たちを見捨てない」という象徴だった。
しかし今、その制度が**“コストに見合わない”**という理由で、事業仕分けの場に呼び出され、“整理対象”とされている。
その判断の先頭に立っているのが、「寄り添う市政」を掲げて当選した森正一市長である。
◆ 仕分けの現場で起きていたこと
2023年、館山市が実施した事業仕分けの議論では、この制度についてこう整理された:
-
制度の利用者は約900人中385人(利用率42%)
-
利用しない理由の調査は未実施
-
手続きが煩雑、窓口負担が障壁になっている可能性も指摘
-
年間予算:約2500万円、うち人件費600万円
-
他市町村では実施されておらず、「館山だけが残っている」と説明
だが、議論のなかで最も切実だったのは、市民=当事者の声だった。
◆ 傍聴者が語った「現実の声」
会場にいた一人の女性が、涙をこらえながら発言した。
「私の息子は先天性の障害があります。30歳を過ぎてからも、加齢とともに新たな障害が増え、東京の病院まで通わなければならないこともある。この制度がなければ、通院も治療も成り立たない。削減されたら生活が立ち行かなくなる。」
さらにこうも訴えた。
「今回の仕分けの話が出てから、他の障害当事者の家族からも“制度がなくなると困る”という声が多数寄せられている。
それなのに、“制度の意義”が議論されることなく、“使っていない人が多いから見直し”なんて、おかしいと思う。」
制度を「数字」で切り取る仕分け人に対し、彼女の言葉はこう問いかけていた。
「たった600円の支えすら、奪うつもりですか?」
◆ 事業仕分けの判定結果(全39票)
| 判定区分 | 内容 | 票数 |
|---|---|---|
| ① 不要・凍結 | 制度としての継続不要 | 9票 |
| ② 県との連携 | 館山市単独でなく県レベルで再構築 | 4票 |
| ③ 実態把握の上で継続 | 必要だが、利用者実態をまず調査すべき | 21票 |
| ④ 現状維持 | このまま継続 | 4票 |
➡ 削減に“イエス”を出したのは少数派。
だが、市はこの結果を“見直しの根拠”にしようとしている。
◆ 子どもには拡大、障害者には削減――“二枚舌”の福祉政策
森市長は選挙公約として、こう語っていた。
「高校生までの医療費助成を拡大したい。」
一方で、障害者への医療費助成には削減の判断が迫られている。
同じ「医療費助成」でも、“守られる人”と“削られる人”がいるのはなぜか?
“声の大きさ”が支援の有無を決めるなら、それは選別であり、排除ではないか?
◆ 「大きな事業は止めない、小さな事業は見直す」の欺瞞
森市長はこうも述べている。
「進んでいる大きな事業を、すぐにストップする考えはない。」
ならば問いたい。
なぜ2500万円規模の“ささやかな支え”から切り捨てようとするのか?
それは、最も声を上げにくい人々への支援だからではないのか?
◆ 図表で見る:館山市の“選別福祉”の構図
◯ 図1:対象者と利用者(R4年度)
-
利用者:385人(42%)
-
未利用者:530人(58%)
◯ 図2:制度費用と効果(R4年度)
| 指標 | 金額または件数 |
|---|---|
| 年間予算 | 約2,500万円 |
| 1人あたり助成額 | 約60,000円 |
| 自己負担(1回) | 600円 |
| 申請回数(計) | 約1,400件 |
◯ 図3:他自治体の実施状況(千葉県内)
| 自治体 | 実施状況 |
|---|---|
| 館山市 | ○ |
| 南房総市 | × |
| 鴨川市 | × |
| 木更津市 | × |
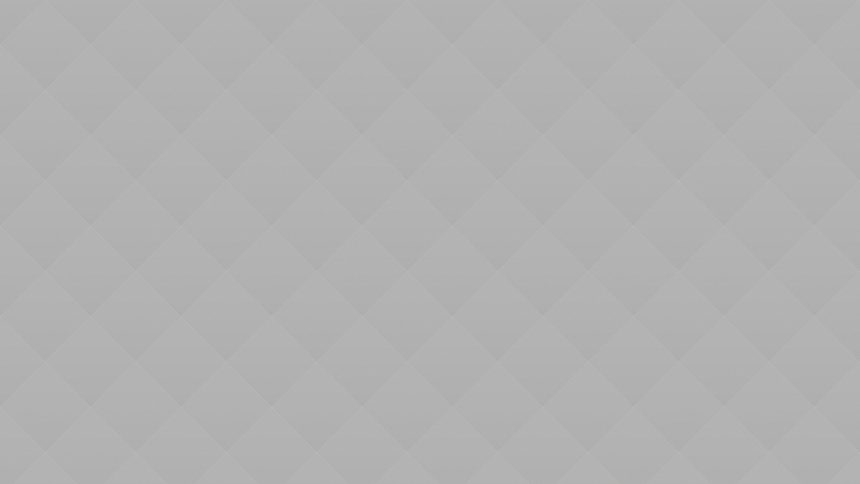
Leave a Reply